レプトスピラは予防した方がいいの?感染した場合の治療なども詳しく解説
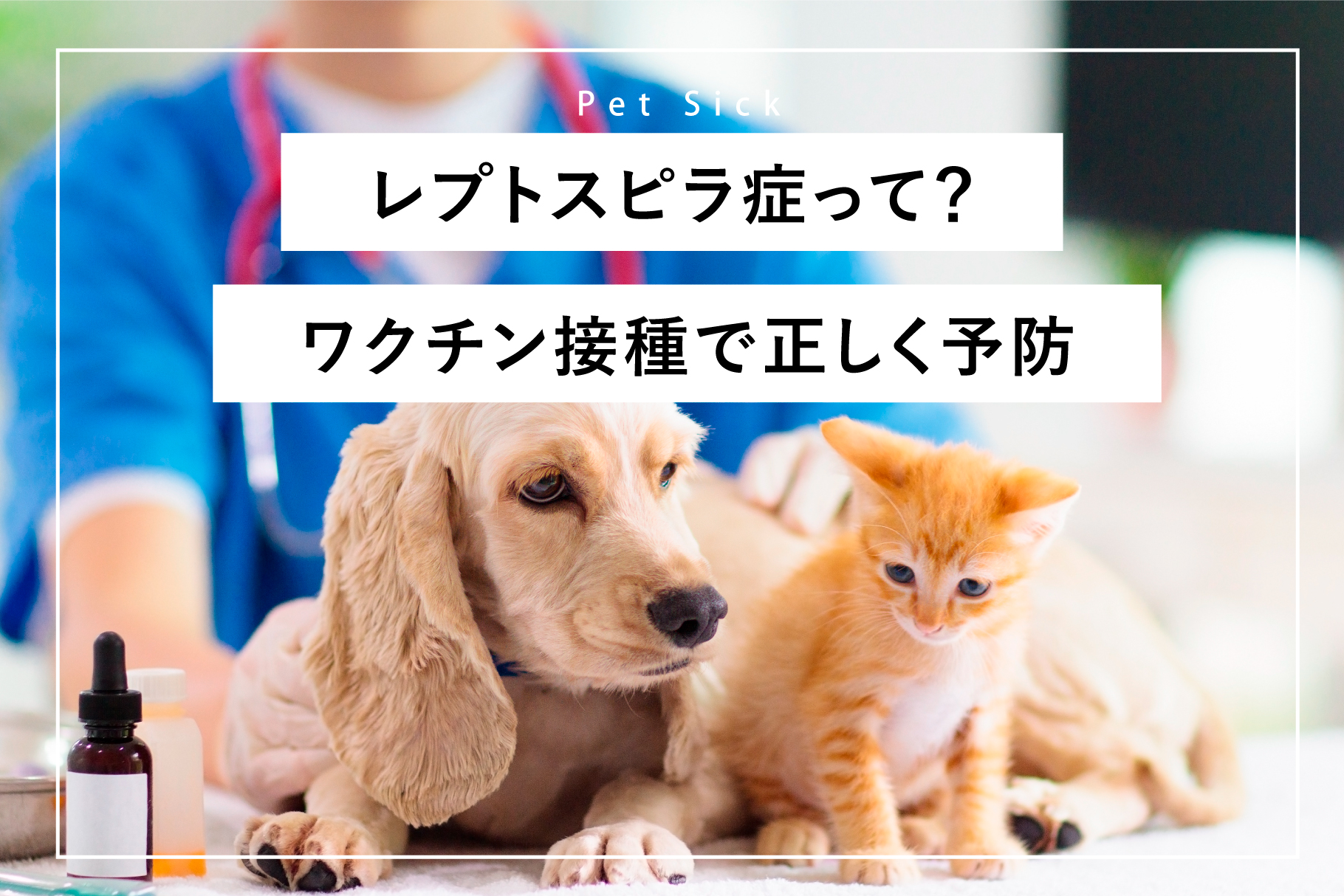
レプトスピラ症は、「レプトスピラ菌」という細菌によって引き起こされる感染症です。犬だけでなく、人にも感染する「人獣共通感染症(ズーノーシス)」であるため、飼い主さん自身にも関わる病気です。
近年、人と動物の両方に関わる「人獣共通感染症」として注目されているレプトスピラ症。 これまで「西日本の病気」と思われがちでしたが、関東地域でも感染報告が増加傾向にあります。 この記事では、柏市周辺にお住まいの飼い主の皆さまへ向けて、レプトスピラ症の特徴・感染経路・発生状況・予防方法など、知っておきたい情報をわかりやすくまとめました。
レプトスピラ症とは?
Leptospira(レプトスピラ)属の細菌によって引き起こされる感染症で、主に以下のような症状を引き起こします。
- 発熱、震え、筋肉痛
- 嘔吐、下痢、脱水
- 黄疸(皮膚や目が黄色くなる)
- 鼻出血、下血、点状出血などの出血傾向
- 重症化すると、肝不全・腎不全・播種性血管内凝固(DIC)
- まれに突然死に至ることもあります。
「西日本の病気」ではなくなってきた
レプトスピラ症はかつては、九州・四国・沖縄などの温暖湿潤な地域に多いとされていましたが、近年では関東でも感染報告が増えています。
関東での発生例(抜粋)
- 2024年:千葉県全体で5例の感染報告があります。
- 2025年:船橋市で2例、市原市で1例の報告があります。
ネズミが主な感染源に
レプトスピラ菌は、ドブネズミやクマネズミなどのげっ歯類が自然宿主とされ、症状が出ないまま尿中に長期間菌を排出し、環境を汚染します。 都市部でも約10~20%のネズミが菌を保有していたという報告があり、見た目が清潔な環境でも感染源となり得ることがあります。
ワクチン接種は必要?リスクと判断基準
犬用のレプトスピラワクチンは、感染リスクに応じて接種の必要性を判断することが重要です。 特に、川や池、湿地などに近づく機会がある犬や、アウトドア活動が多い犬は感染リスクが高まります。 また、ワクチンは特定の血清型にしか対応しておらず、すべての菌株に対する予防はできない点も考慮しましょう。
接種が推奨される例
- 自然水域や湿地に近づく機会がある
- アウトドアやキャンプに同行する
- 多頭飼育や他の犬との接触機会が多い
- 感染例が報告されている地域に住んでいる
ワクチン接種に伴う2つの注意点
- レプトスピラを含むワクチンは、レプトスピラを含まないワクチンに比べて、有害事象(副反応)の発生率がやや高い傾向があります。状況によっては一時的な発熱・元気消失などが見られることがあります。まれにアレルギー反応もあります。
- すべてのレプトスピラ血清型をカバーしているわけではありません。ワクチンが対応していない型による感染リスクは残ります。
完全室内飼育や短時間散歩など、感染リスクが極めて低い犬には不要な可能性もあります。副作用リスクや費用対効果も考慮し、獣医師と相談しながら慎重に判断するようにしましょう。
飼い主としてどれくらい注意したらいいの?
レプトスピラ症は、まれに重症化や突然死を引き起こすこともある感染症です。しかし感染リスクは、犬のライフスタイルによって大きく異なります。過度な心配は不要ですが、自分の犬にとって本当に必要な予防策を選ぶことが大切です。 迷ったときは、かかりつけの動物病院で相談し、ワクチンの必要性や感染対策について一緒に考えていきましょう。少しでもご心配なことがあれば岡部獣医科病院にお気軽にご相談ください。




